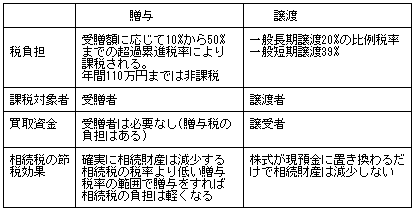Ⅲ.不動産贈与と税務
■一般贈与を活用する場合
(1)一般贈与の概要
①贈与とは
贈与とは、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思表示をし、相手方がこれを受託することによって成立する契約のことをいいます。
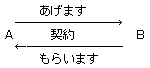
②贈与があったときとは
贈与がいつあったかは、次のように取り扱われます。
イ.書面によるものは、その贈与契約の効力の発生の時
ロ.書面によらないものは、その贈与の履行のあった時、ただし、停止条件
が付いているものについては、その条件が成就したとき
ハ.農地などの場合は、農地法の許可のあった日又は届出の効力のあった日
ニ.所有権の移転の登記又は登録の目的となる財産で、贈与の日が明確でな
いものについては、その登記又は登録があった時
③贈与税の対象となる財産・ならない財産
イ.贈与税の対象となる財産
贈与税の対象となる財産は、次の本来の贈与財産とみなし贈与財産です。
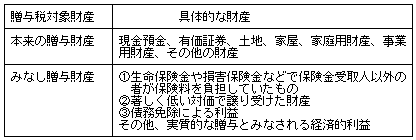
ロ.贈与税の対象とならない財産
次のような財産は、贈与税の対象になりません。
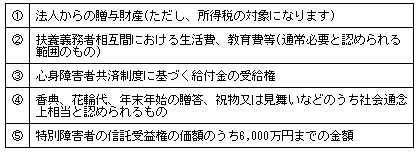
④贈与があったとみなされるとき
税務では、次のような場合も、贈与があったものとして取り扱われます。
イ.不動産や株式等の名義変更があった場合において対価の授受がなされて
いないとき
ロ.他人名義で不動産や株式を取得した場合
また、次のような場合には、外見的な形式ではなく、その実質にしたがって贈与があったかどうか判断されます。
ハ.親名義の不動産や株式などを子供に贈与したが、形式的には親子間の売
買として名義変更した場合
ニ.親が新たに不動産や株式などを他の者から取得し、これを子供に贈与し
た場合において、登記上、子供が直接売買により取得した形式をとって
いるとき
ホ.妻又は子供が不動産や株式などを直接他の者から取得し、自分の財産と
したときにおいて、その買入資金が夫又は親から出ている場合
⑤贈与税の納税義務と対象財産の範囲
納税義務者は、贈与によって財産を取得した個人ですが、個人の住所がどこにあるかによって、対象財産は次のように取り扱われます。
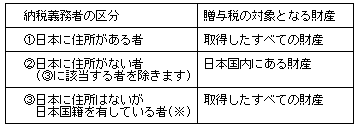
(※)受贈者又は贈与者がその贈与の日前5年以内において日本国内に住所を有したことがある場合に限ります。
(2)贈与税の計算方法
贈与税額は、次の手順で計算します。
①贈与税の課税対象財産を求める
課税対象財産は、その年の1月1日から12月31日までの間に贈与によって取得した財産の価額を合計して求めます。
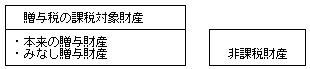
②贈与税の基礎控除を差引く
![]()
①で求めた課税価格から贈与税の基礎控除110万円を控除します。
③配偶者控除の適用(? 参照してください)を受ける場合
贈与税の配偶者控除の適用を受ける場合は、ここから配偶者控除の額(最高2,000万円)を控除します。
④贈与税額を求める
②又は③で求めた金額(千円未満は切り捨てます)を次の速算表にあてはめて贈与税額を計算します(百円未満の金額がある場合は切り捨てます)。
(例)基礎控除後の課税価格が300万円の場合
基礎控除後
の課税価格 税率 控除額 贈与税額
贈与税額=300万円 × 15%-10万円=35万円
[贈与税の速算表]

(3)贈与税の申告と納税
贈与税の申告書は、贈与年の翌年2月1日から3月15日までの間に、納税地を所轄する税務署長に提出しなければならず、その申告書を提出した者は、その提出期限までに申告書に記載された贈与税額を国に納付しなければなりません。ただし、贈与税額が10万円を超える場合において、納期限までに又は納付すべき日に金銭で納付することを困難とする事由があるときは、その納付を困難とする金額を限度として、5年以内の期間で、年賦延納することができます。
①申告書の提出期限と贈与税の納付期限
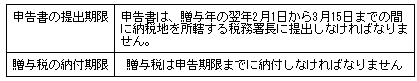
②贈与税の延納
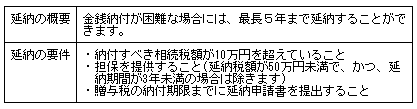
(4)生前贈与分岐点
贈与税は、相続税の補完税としての性格を有していますから、その税率は相続税より高くなっています。しかし、贈与税には1人当たり110万円の基礎控除額がありますので、計画的に贈与を実行していけば相続税は確実に減ることとなります。どれぐらい贈与するのがいいのかは、現状において予想される相続税の実効税率の贈与税の実効税率が等しくなる生前贈与分岐点を目安のするといいでしょう。
(例)
・相続財産 3億円
・相続人 3人
・相続税額 4,500万円(配偶者控除は考慮しません)
①相続税の実効税率を求めます。
相続税の実効税率=4,500万円
──── =15%
3億円
②贈与税の実効税率表に①をあてはめます。
贈与税の実効税率表から15%となる範囲を求めます。そうしますと、贈与価額(基礎控除を含んだ金額です)が650万円から少し超えたところが15%になるのがわかります。
[贈与税の実効税率表]
③贈与税の速算表にあてはめます
650万円から基礎控除110万円を差し引いた金額(540万円)の贈与税率を速算表から求めます。すると、税率が30%、控除額が65万円というのがわかります。
[贈与税の速算表]
④生前贈与分岐点を求めます。
これを使って生前贈与分岐点を求めます。
0.3x - 65万円 =0.15
────────
x + 110万円
生前贈与分岐点(x)=653万3,000円
この生前贈与分岐点653万3,000円までの金額を贈与をする場合に、税負担が軽減されます。
2.相続時精算課税制度の贈与を活用する場合
■相続時精算課税制度の概要
(1)相続時精算課税制度とは
「相続時精算課税制度」とは、65歳以上の親から20歳以上の子供への贈与に認められた贈与の特例で、2,500万円までの贈与は非課税、それを超える部分の金額に対しては、一律20%の税率で贈与税がかかるというものですが、その贈与した財産の価額は、相続時に相続財産として持ち戻し(加算)をして相続税を計算し、その際に納めた贈与税額があるときは、これを精算(相続税額から控除)して課税するというものです。
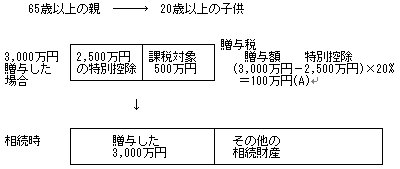
[相続税の計算]
相続財産と相続時精算課税制度により贈与した財産を合計して
相続税額を計算し、その税額からすでに納めた贈与税額(A)を
差し引き、納めるべき相続税額を求めます。
この制度を活用しますと、2,500万円までの贈与であれば贈与税がかからず、また、2,500万円を超える部分があっても、20%という低い税率(通常の贈与であれば50%の税率がかかります)で計算した税額を納めるだけで済みますので、大きな財産を生前贈与できるというメリットがあります。
(2)適用対象者
この制度の対象となる人は、次のとおりで、満65歳の親から満20歳以上の子(推定相続人)に対して行う贈与に適用があります。
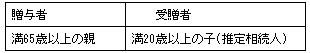
※子供が親より先に亡くなっている場合は、その子供(孫)が満20歳以上であれば、その孫にも適用があります。
なお、この規定は、父、母ごとに、また子供ごとに適用選択ができますので、たとえば、次のように父親から長男には適用するが、母親から長男には適用しないとすることもできますし、兄弟のうち一人だけに適用するということもできます。
つまり、片親だけに適用することもできますし、両親共に適用を受けることもできるわけですが、両親から受ける場合には、父からの分2,500万円と母からの分2,500万円の合計5,000万円の特別控除が使えることになるわけです。
通常の贈与のように、もらったもの全部合計したものから基礎控除の110万円控除するというのとは、少し違いますので区別しておいてください。
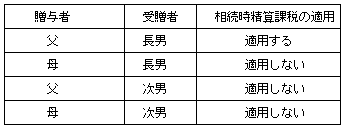
ただし、この規定は、一度選択すると二度と取り消しができないので、選択の際は慎重にしなければならなりません。
(3)年齢は満年齢か
贈与税は、暦年基準を採用していますから、その贈与のあった年の1月1日現在での年齢で判定することとしています。
したがって、贈与者については、贈与のあった年1月1日現在で満65歳以上になっている、また、受贈者については、その贈与にあった年1月1日現在で満20歳以上になっていることが必要です。
その年に満65歳又は満20歳になっていれば適用があるということではありませんので、くれぐれも注意してください。
(4)養子の取り扱い
この特例は、実子だけでなく、養子縁組をした子にも適用があります。
したがって、養子となった子でも、年齢基準を満たしておれば、養父母からも実の親からもこの適用を受けることができることとなります。
年齢基準は、その年の1月1日現在で判断しますが、養子がこの規定の適用を受けるためには、その年1月1日において養子と養親という関係になければなりませんので注意してください。
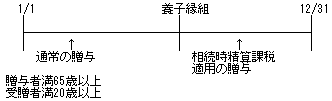
なお、この規定は、養父、養母、または、実父、実母ごとに選択適用することができます。
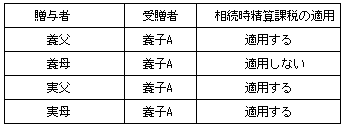
(5)養子縁組を解消した場合
養子縁組を解消した後に相続が発生した場合は、相続時にたとえ養子縁組が解消されていたとしても、生前に相続時精算課税制度を使って贈与した財産は、養親からの相続財産とみなして相続税が課税されます。
この場合には、元養子は養子(相続人)でなくなっていることから、その元養子の相続税については、相続税額の2割加算の規定が適用されることとなります。
ただし、受贈者が、1親等の血族であった期間内に贈与により取得した財産に対応する相続税額として、
次の算式で計算した金額については、2割加算の対象となりません。
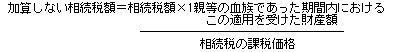
なお、この取り扱いは、受贈者が廃除や欠格などにより、贈与者の推定相続人に該当しなくなった場合においても同様に取り扱われます。
(6)受贈者が贈与者より先に死亡した場合
相続時精算課税制度の適用を受けた受贈者(子)が、贈与者(親)より先に死亡した場合は、次のように取り扱われます。
イ.受贈者の相続税の計算
子の相続財産には、子自身の本来の財産と親から贈与を受けた財産とがあ
りますが、子の相続税を計算する場合には、通常通り、すべての財産に対
して相続税を計算します。
ロ.贈与者の相続税の計算
親(祖父)が亡くなったときは、孫が代襲相続人として祖父の相続をすることになりますが、この場合には、自分の親(子)が祖父から受け取った贈与財産を相続により取得したものとみなして相続税を計算し、親(子)が相続時精算課税制度により納めた贈与税額があるときは、これを相続税額から控除して精算することとなります。
つまり、この制度を受けた受贈者が贈与者より先に死亡した場合には、そ
の受贈者の相続人は、受贈者が有していたこの制度にかかる権利又は義務
を承継することとなるわけです。
なお、子の相続人が2人以上いるときは、法定相続分に応じてこれを承継
することなります。
(7)適用回数
この特例には、贈与回数や贈与年数の規制はありませんので、何回でも、また、何年にわたってもいいのですが、一度この制度を選択しますと、二度と通常の贈与をすることができず、一生この特例贈与を使い続けなければなりませんので、その点十分注意してください。
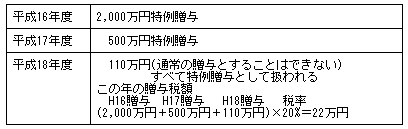
(8)財産の価額
この制度を選択した場合には、その選択した贈与財産は、その親の相続時に相続財産に加算して相続税を計算することとされているが、この場合の相続税に加算される贈与財産の価額は、相続時の価額ではなく、贈与したときの価額によることとされています。
したがって、不動産のように価額変動を伴う財産を贈与するような場合には、その財産が値上がりするのか、または値下がりするのかを見極めて贈与する必要があり、注意しなければなりません。
また、この取り扱いは、贈与を受けた財産が、別の財産に置き換わっていたとしても、同じ取り扱いがされます。
■相続時精算課税制度における贈与税額の求め方
(1)贈与税額の求め方
この特例の適用を受ける場合の贈与税額は、次の算式で求めます。
その年中において 前年までに特例 特別控除
(特例贈与を受けた + 贈与を受けた財 -2,500万円) ×20%=贈与税額
財産の価額 産の合計額
また、父親からと母親から特例贈与を受けた場合には、父親からの贈与税額と母親からの贈与税額をそれぞれ合計したものがその年の贈与税額となります。
(例)
父親からの贈与 4,000万円
母親からの贈与 3,000万円の場合
父親からの贈与に対する税額
特別控除
(4,000万円-2,500万円)×20%=300万円
母親からの贈与に対する税額
特別控除
(3,000万円-2,500万円)×20%=100万円
納める税額
300万円+100万円=400万円
なお、その年分において、たとえば、父親からは特例贈与を受け、母親からは通常の贈与を受けているという場合には、次のように贈与税額を計算します。
(例)
父親からの特例贈与 4,000万円
母親からの通常の贈与 200万円
父親からの贈与に対する税額
特別控除
(4,000万円-2,500万円)×20%=300万円
母親からの贈与に対する税額
通常の基礎控除 贈与税率
(200万円-110万円)×10% =9万円
納める税額
300万円+9万円=309万円
(2)手続き
この相続時精算課税制度の適用を受けるには、次の手続きをしなければなりません。
①選択届出書の提出
この規定の適用を受けようとする受贈者は、その選択をしようとする最初の贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、納税地の所轄税務署長に対して、選択届出書を提出しなければならなりません。
②贈与税の申告書の提出
また、この規定の適用を受ける場合には、たとえその年の贈与税額がゼロであっても、贈与税の(期限内)申告書を提出しなければなりませんので、忘れないようにしてください。
選択届出書の届け出もなく、また、申告書の提出もない場合は、通常の贈与があったものとして贈与税が課税されることになり、この場合には無申告加算税や延滞税も課税されますので注意してください。
なお、納めるべき贈与税額がある場合は、贈与税の申告期限までに贈与税額を国に納めなければなりません。
■相続時の相続税額の求め方
この制度を活用した場合の相続税額は、次のように計算します。
①相続時精算課税適用者の課税価格の計算
相続又は遺贈により取得した財産の価額
+
相続又は遺贈により取得したとみなされる財産の価額(生命保険など)
+
相続時精算課税対象財産の価額(A)(贈与時の価額)
-
債務及び葬式費用の額
+
相続開始前3年以内に取得した財産(Aを除く)
=
課税価格
②相続時精算課税不適用者の課税価格の計算
相続又は遺贈により取得した財産の価額
+
相続又は遺贈により取得したとみなされる財産の価額(生命保険など)
-
債務及び葬式費用の額
+
相続開始前3年以内に取得した財産
=
課税価格
③課税遺産総額を計算する
(①+②)-遺産にかかる基礎控除額=課税遺産総額
④各法定相続人の法定相続分に応ずる取得金額を計算する
⑤④に対する相続税額を求め、それを合計する(相続税額の総額の計算)
⑥⑤を取得した財産額で按分する
⑦各人の納付すべき相続税額を計算する
⑧相続時精算課税制度適用者の還付税額を計算する
これを設例でみてみますと、次のようになります。
(例)
父親が死亡
・相続財産2億円
・相続時精算課税制度適用財産4,000万円(イ)
・相続時精算課税制度適用時の贈与税額300万円
・相続人 母親、長男(相続時精算課税制度適用)、次男
・分割割合 母親1/2(1億2,000万円) 、長男1/4(2,000万円+(イ)=
6,000万円)、次男1/4(6,000万円)とすると
①相続時精算課税適用者の課税価格の計算
2,000万円+4,000万円=6,000万円
②相続時精算課税不適用者の課税価格の計算
母親1億2,000万円+次男6,000万円=1億8,000万円
③課税遺産総額を計算する基礎控除額
(①+②)-{5,000万円+(1,000万円×3人)}=1億6,000万円
④各法定相続人の法定相続分に応ずる取得金額を計算する
・母親
1億6,000万円×1/2=8,000万円
・長男、次男
1億6,000万円×1/4=4,000万円
⑤相続税額の総額の計算
・母親分
8,000万円×30%-700万円=1,700万円
・長男、次男分
(4,000万円×20%-200万円)×2=1,200万円
・合計2,900万円
⑥⑤を取得した財産額で按分する
・母親分
2,900万円×1/2=1,450万円
・長男、次男
2,900万円×1/4=725万円
⑦各人の納付すべき相続税額を計算する
・配偶者
→配偶者に対する税額の軽減により納付税額ゼロ
・長男
贈与税額
725万円-300万円=425万円
・次男
725万円
■贈与した場合の効果
この制度は、生前に贈与した財産は、相続時に、贈与時のその財産の価額で持ち戻し(加算)して相続税を計算しますので、他の相続財産が変わらない限り、相続税額は、この特例を使っても使わなくても同じになります。
(例)相続財産 2億5,000万円
相続人 子供2人
①相続時精算課税制度を活用して5,000万円贈与した場合
イ.贈与税
(5,000万円-2,500万円)×20%=500万円
ロ.相続税
相続財産2億円+5,000万円=2億5,000万円
2億5,000万円に対する相続税=4,000万円
納税額=4,000万円-500万円(贈与税額)=3,500万円
ハ.合計
500万円+3,500万円=4,000万円
②相続時精算課税制度を活用しない場合
相続税
2億5,000万円に対する相続税=4,000万円
このように、この特例には、相続税の節税効果は基本的にありませんので、相続税の節税をと考えられるのであれば一般の贈与を使う方がメリットがあります。
一般の贈与の場合、たとえば、このケースで、500万円ずつを10年間贈与したとすると、税負担は次のようになります。
①贈与税
(500万円-110万円)×20%-25万円=53万円
53万円×10年=530万円
②相続税
相続財産 2億5,000万円-5,000万円=2億円
2億円に対する相続税=2,500万円
③税負担額
①+②=3,030万円
④節税額
4,000万円-3,030万円=970万円
つまり、相続税の節税だけを考えるなら、一般の贈与を活用し、この制度は使わない方が有利なわけです。
■活用のポイント
では、この制度は、どんな人がどのように活用するとよいか、これをみてみましょう。
(1)どんな人が使うとよいか
①相続税がかからない人
相続時精算課税制度の対象とした贈与財産は、相続税の計算をする際に持ち戻し(加算)して計算することとされていますが、相続税がかからない人であれば、持ち戻しされても一向にかまわないわけですから、こういった人は、積極的に2,500万円までの範囲で贈与するとよいでしょう。
②相続税の実効税率が20%以内の人
相続時精算課税制度のよる贈与は、2,500万円までは贈与税がかかりませんが、それを超えると一律20%の贈与税が課税されます。
したがって、相続税がかかる人のうち、その実効税率が20%以内の人については、税額を先に払うか後に払うかという違いはありますが、早い段階で財産の移転ができ、また、計画的に行えるという点で活用するメリットはあるのではないでしょうか。
③相続税の実効税率が20%を超える人
? 相続税の実効税率が20%を超える人は、この規定の適用を受けても、贈与した財産を持ち戻す(加算)こととなるため、あまり、相続税の節税にはならないのですが、次のような効果もあるので活用を検討してみてください。
イ.特定の財産を、生前に承継できる
ロ.このことによって、遺産分割をめぐるトラブルを解消できる
ハ.事業承継者には、自社株など経営に必要なものを渡しておくことができる
ニ.あらかじめ、各相続人への財産の配分を決めておける
ホ.贈与であるから、確実に当人に財産の移転ができる
ヘ.とりあえずは、20%の贈与税で移転ができる
(2)どのように活用するとよいか
この相続時精算課税制度は、次のように活用することができますので、その目的に応じて活用すればよいでしょう。
①資金援助
一般的な使い方としては、子供への資金援助があります。
ローンの返済資金であるとか、車の購入資金、住宅資金の頭金として活用することができますが、住宅の購入を手助けしてやるのであれば、現金を贈与するより、住宅を建ててからその住宅を贈与する方が税負担が軽くてすみます。
住宅で贈与すると、土地は路線価評価などの相続税評価、建物は固定資産税評価となり、いずれも購入価額より低い評価額になるからです。
②所得税対策
親の所得税が高い場合には、その収益を生み出す物件を子供に贈与することによって、所得税の負担を軽くすることができます。
たとえば、立体駐車場の駐車場部分だけ(土地はそのまま親の名義)、親から子へこの制度を活用して贈与すれば、親の所得は減り、子の所得が増えることとなります。
③相続対策
収益物件を子供に贈与すれば、その時点から、その物件がもたらす財産の増加を防ぐことができます。また、将来的に評価が上昇していくと思われる財産は、早い時点で贈与することによって、その値上がり部分を相続に影響させずにすみますので、その点において相続税対策となります。
④生前遺産分割
この制度を活用して、財産を生前に各子供に移転しておけば、相続時の分割をめぐるトラブルが防げます。
また、遺言と組み合わせれば、財産の配分調整が可能となり、一層スムーズな相続ができます。
(3)どんな財産を贈与するとよいか
どんな財産をあげるとよいかは、この制度をどのような目的で使うかによって違ってきます。
①資金援助
一時の資金援助を目的とするのであれば、現金でしょうが、コンスタントに入ってくる収入を手当てするというのであれば、収益物件の贈与になるでしょう。
②所得税対策
収益物件を贈与すれば、親の所得税対策になります。また、子供はそこから上がってくる収入を蓄えておけば、相続税の納税資金として活用することができます。
③相続対策
財産の価額が上がっていくと見込まれるものは早いうちに贈与するとよいでしょう。そうすれば、子供の資産形成にも役立ちます。
■小規模宅地等の特例との関係
(1)贈与時の取り扱い
小規模宅地等の特例は、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた親族が、事業の用又は居住の用に供していた宅地等を、相続人等が「相続又は遺贈により」取得した場合に認められるものです。
?? したがって、「贈与により」取得した宅地等には、小規模宅地等の特例を適用することはできません。それは、その宅地等が、相続時にこの適用が受けられる宅地等であったとしても同じことです。
(2)相続時の取り扱い
では、相続時に、相続時精算課税制度の適用を受けた贈与財産にこの特例の適用があるかといいますと、この場合も、取得原因が「贈与」ですから適用はありません。
相続時精算課税制度による贈与財産は、贈与者の相続時に相続財産に加算されますが、これは、相続により取得するのではなく、その贈与した財産の価額を相続財産に、計算上加算するにすぎないのです。
■特定事業用資産の特例との関係
(1)贈与時の取り扱い
特定事業用資産の特例とは、相続又は遺贈(相続時精算課税制度による贈与を含みます)により取得した取引相場のない株式等(自社株など)のうち、発行済株式総数の3分の2以下に相当する部分(3億円を限度とします)については、次の要件を満たす場合に限り、相続税の課税価格を10%減額してくれるという特例ですが、この特例は、被相続人から相続人等が「相続又は遺贈により取得」した場合に適用があるものです。
したがって、「贈与により」取得した株式等には、特定事業用資産の特例を適用することはできません。
①その会社の発行済株式等の総額(相続税評価額ベース)が20億円未満である
こと
②被相続人及び被相続人の親族その他被相続人と特別の関係がある者がその会社の発行済株式等の総数の50%超を所有していること
③被相続人の親族がその会社の株式等を相続等により取得し、これを相続税
の申告期限まで引き続きそのすべてを有していること
④相続税の申告期限を経過する時において、その会社の株式等を相続等した
被相続人の親族がその会社の役員等であること
(2)相続時の取り扱い
ただし、相続時精算課税制度を活用して贈与された特定事業用資産の対象となる株式等は、相続時においては、この特例の適用を受けることができるとされています。これは、この特定事業用資産の特例が、中小企業者の事業承継を円滑に進めるという目的で創設されたものだからです。この点は、小規模宅地等の特例の取り扱いと異なります。
なお、この場合の減額対象となる金額は、贈与時の評価額を基に計算されるとされています。
■一般贈与と相続時精算課税制度の贈与の違い
(1)一般贈与と相続時精算課税制度の贈与との相違点
一般の贈与と相続時精算課税制度による贈与との相違点は、次にようになっています。
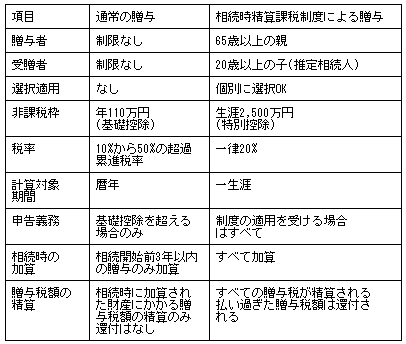
(2)一般贈与と相続時精算課税制度の贈与のメリット、デメリット
一般の贈与と相続時精算課税制度による贈与のメリット、デメリットは次のようになっています。
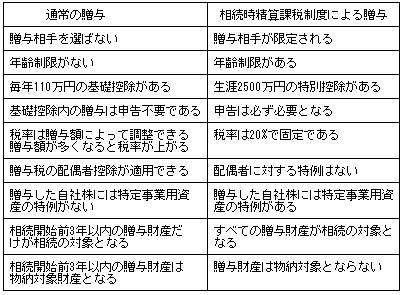
3.住宅型精算課税制度の贈与を活用するケース
■住宅型精算課税制度の概要
(1)住宅型相続時精算課税制度とは
2の相続時精算課税制度は、財産の種類や資金使途を問わない贈与の特例ですが、資金使途を住宅の取得や増改築に限定した贈与にも相続時精算課税制度とほぼ同じ内容の制度があります。これを、ここでは住宅型相続時精算課税制度と呼びます。
「住宅型相続時精算課税制度」とは、親から満20歳以上の子供へ自宅の取得資金を贈与する場合に認められる贈与の特例で、3,500万円までの贈与は非課税、それを超える部分の金額に対しては、一律20%の税率で贈与税がかかるというものですが、その贈与した財産の価額は、相続時に相続財産として持ち戻し(加算)をして相続税を計算し、その際に納めた贈与税額があるときは、これを精算(相続税額から控除)して課税するというものです。
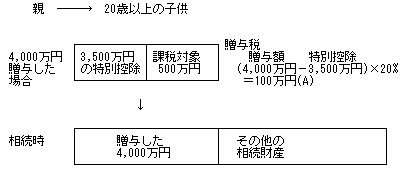
[相続税の計算]
相続財産と相続時精算課税制度により贈与した財産を合計して
相続税額を計算し、その税額からすでに納めた贈与税額(A)を
差し引き、納めるべき相続税額を求めます。
この制度の大枠は、相続時精算課税制度と同じですが、贈与財産が特定され、かつ、贈与財産の使途が限定されているなどの制約がある半面、贈与者の年齢制限がない、また特別控除額が3,500万円(1,000万円+2,500万円)認められているという点で違いがあります。
違いは、次のようになっています。
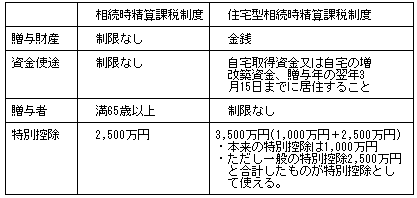
(2)相続時精算課税制度と併用する場合
相続時精算課税制度とこの住宅型相続時精算課税制度は、上記のような点に違いがありますが、上記以外の点については、相続時精算課税制度を準用することとされていますので、この節で説明していない項目については、2の相続時精算課税制度の取扱いを参照してください。
なお、この制度と相続時精算課税制度との併用については、次のように取り扱われることとされています。
①特別控除の取り扱い
住宅型相続時精算課税制度の特別控除の3,500万円というのは、相続時精算課税制度で認められている2,500万円とこの規定で認められている1,000万円の合計金額のことですから、住宅型相続時精算課税制度で3,500万円、相続時精算課税制度で2,500万円適用できるということではありませんので注意してください。
②控除不足の取り扱い
たとえば、62歳の贈与者が、子供に住宅取得資金1,500万円を贈与して、子供がこの特例を受けた場合には、2,000万円(3,500万円-1,500万円)の特別控除が余りますが、この2,000万円の特別控除は切捨てになってしまうというわけではなく、相続時精算課税制度の特別控除として使えることとなります(この場合には、同一の贈与者からの贈与であれば、満65歳になっていなくても特例が受けられます)。もちろん、家の増改築資金の贈与にも適用があります。
これに対して、住宅資金の贈与が800万円であって、200万円(住宅型の特別控除は1,000万円)使い残したという場合には、次のように取り扱われます。
イ.住宅取得資金の贈与を受けた場合
更に住宅取得資金(増改築等)の贈与を受ける場合には、余りの200万円と
相続時精算課税制度に認められている2,500万円との合計金額2,700万円の
特別控除が使えます。
ロ.住宅取得資金以外の贈与を受けた場合
住宅取得資金以外の贈与を受けた場合は、住宅型相続時精算課税制度の
200万円は切り捨てになり、相続時精算課税制度に認められている2,500万
円の特別控除だけが使えることとなります。
一方、満65歳を超えた贈与者が、住宅取得資金以外の贈与を800万円し、その後、住宅取得資金の贈与をするという場合には、相続時精算課税制度の特別控除の余り1,700万円(2,500万円-800万円)と住宅型相続時精算課税制度の特別控除の1,000万円との合計2,700万円が使えることとなります。
(3)適用対象者
この制度の対象となる人は、次のとおりです。
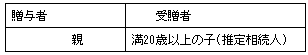
贈与者の親には、相続時精算課税制度のような年齢制限がありませんので、満65歳以上でなくても贈与することができますが、受贈者には、相続時精算課税制度同様、満20歳以上という年齢制限がありますので間違わないようにしてください。
なお、この制度は、贈与者ごと、また受贈者ごとに適用が受けられることとなっていますので、たとえば、父親から長男への贈与には適用するが、次男への贈与には適用しないということもできますし、父親からも母親からも長男への贈与には適用するといったこともできます。
両親それぞれからの贈与に、この適用を受ければ最高7,000万円(養父母がいる場合には養父母からの贈与にも適用があり、この場合には合計1億4,000万円)までが非課税とすることができます。
なお、両親の年齢が満65歳以上の場合には、たとえば、父親からの贈与については住宅型相続時精算課税制度の適用を受け、母親の贈与については相続時精算課税制度の適用を受けるということもできるのでこうしたことも検討するとよいでしょう。
(4)対象となる住宅
適用対象となる住宅の要件は、次のとおりです。
①取得、建築する場合
イ.新築又は築後経過年数が20年以内(一定の耐火建築物である場合は25年以
内)であること
ロ.家屋の床面積(区分所有の場合は、その区分所有する部分の床面積)が50
㎡以上であること
ハ.その家屋の床面積の2分の1以上がもっぱら居住の用に供されていること
ニ.居住の用に供する家屋が2以上ある場合には、これらの家屋のうち主とし
て居住の用に供すると認められる一つの家屋
ホ.その他、一定の要件を満たすもの
②増改築の場合
自宅の増築、改築、大規模な修繕、模様替え、その他の工事で次の要件を満たすものに適用がある。
イ.増改築の工事費用が、100万円以上であること
ロ.増改築後の家屋の床面積(区分所有の場合は、その区分所有する部分の床
面積)が50㎡以上であること
ハ.その他、一定の要件を満たすもの
③土地部分の取扱い
①や②の取得、増改築等とともにするその敷地の用に供されている土地又は借地権等の取得については、この特例の対象となる。
(5)どんな資金を
住宅型相続時精算課税制度は、一定の自宅((4)を参照ください)を取得するための資金及び一定の自宅を増改築するための資金を贈与する場合に適用がある制度ですから、これらに使われない資金の贈与であったり、これらの要件に合致しない住宅を取得等するための贈与である場合には、この規定の適用が受けられませんので十分注意してください。
贈与者が満65歳以上であり、この規定が受けられなくても、相続時精算課税制度が受けられるという場合であればいいですが、たとえば、贈与者が65歳未満でこの規定の適用が受けられないというような場合には、その贈与については、一般の贈与として取り扱われますので、贈与金額によっては多額の贈与税を納めなければならないといった事態にもなります。要件等のチェックは確実にしてください。
なお、子供が組んだ住宅ローンの返済資金を親が贈与するという場合や、親が建てた子供の自宅を贈与するという場合には、この規定の適用はないので注意してください。
■住宅型相続時精算課税制度における贈与税額の求め方
(1)贈与税額の求め方
住宅型相続時精算課税制度の特例の適用を受ける場合の贈与税額は、次の算式で求めます。
その年中において 前年までに特例??? 特別控除
(特例贈与を受けた + 贈与を受けた財 -3,500万円) ×20%=贈与税額
財産の価額 産の合計額
また、父親からと母親からこの特例贈与を受ける場合には、父親からの贈与税額と母親からの贈与税額をそれぞれ合計したものがその年の贈与税額となります。
(例)
父親からの贈与 4,000万円
母親からの贈与 3,000万円の場合
父親に対する税額
特別控除
(4,000万円-3,500万円)×20%=100万円
母親に対する税額
特別控除
(3,000万円-3,500万円)≦0円? ∴ゼロ
納める税額
100万円
なお、その年分において、たとえば、父親からは特例贈与を受け、母親からは通常の贈与を受けているという場合には次のように贈与税額を計算します。
(例)
父親からの特例贈与 4,000万円
母親からの通常の贈与 200万円
父親に対する税額
特別控除
(4,000万円-3,500万円)×20%=100万円
母親に対する税額
通常の基礎控除 贈与税率
(200万円-110万円) ×10% =9万円
納める税額
100万円+9万円=109万円
(2)手続き
この住宅型相続時精算課税制度の適用を受けるには、次の手続きをしなければなりません。
①選択届出書の提出
この規定の適用を受けようとする受贈者は、その選択をしようとする最初の贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、納税地の所轄税務署長に対して、選択届出書を提出しなければなりません。
②贈与税の申告書の提出
また、この規定の適用を受ける場合には、たとえその年の贈与税額がゼロであっても、贈与税の(期限内)申告書を提出しなければなりませんので、忘れないようにしてください。
選択届出書の届け出もなく、また、申告書の提出もない場合は、一般の贈与があったものとして贈与税が課税されることになります。また、この場合には無申告加算税や延滞税も課税されるので注意してください。
■これまでの住宅等取得資金等の贈与との違い
(1)これまでの住宅取得資金等の取り扱い
これまでの住宅取得資金等の贈与とは、次の一定の要件を満たす贈与について適用があるもので、550万円までは非課税、550万円を超え1,500万円までの部分については特別な計算をして(これを5分5乗方式という)、税負担が軽減されされるという特例です。
①資金使途
イ.自宅の新築または取得に充てられるもの(贈与年の翌年3月15日までにこ
れに居住すること)
ロ.自宅の増改築、大規模修繕
ハ.自宅の買換え又は建替え
②適用対象者
父母又は祖父母から贈与を受けた受贈者で、次の要件を満たすもの
イ.過去にこの特例を受けたことがない者
ロ.贈与を受けた年の合計所得金額(居住用財産の3,000万円控除の適用を受
けている場合はその控除後の金額)が1,200万円以下の者
ハ.贈与前5年以内に自己又は配偶者の所有する住宅(床面積の2分の1以上が
居住用のもの)に居住したことのない者、または住宅の買換えもしくは建
替えのため贈与前5年以内に居住していた自己又は配偶者の所有する住宅
を贈与を受けた年の翌年12月31日までに譲渡又は滅失した者
③対象となる住宅等
イ.家屋の床面積が50㎡以上のもの
ロ.中古住宅の場合は、次の要件を満たすもの
・耐火建築物は、築後25年以内であるもの
・耐火建築物以外のものは、築後20年以内のもの
ハ.次の増改築
・家屋の床面積の増加が50㎡以上のもの
・工事費用が1,000万円以上のもの
④5分5乗方式とは
5分5乗方式とは、次の算式で贈与税額を計算する特例のことである。
イ.贈与年分の贈与税額の計算
贈与税額=(A-B)+B×5
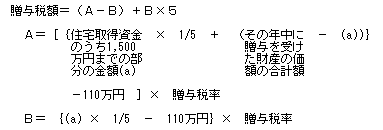
ロ.贈与年の翌年以後4年内の贈与税額の計算
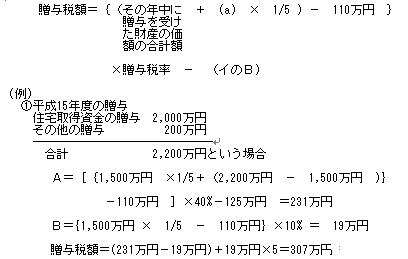
②平成16年度の贈与
その他の贈与 110万円
贈与税額={(110万円 + (1,500万円)× 1/5 ) - 110万円 }
×15%-10万円-19万円=16万円
(2)住宅取得資金等の贈与との相違点
これまでの住宅取得資金等の贈与と住宅型相続時精算課税制度の贈与との違いは、次のようになっています。
これらを考慮して、どちらがいいのか、またどちらが使えるのかを検討してください。
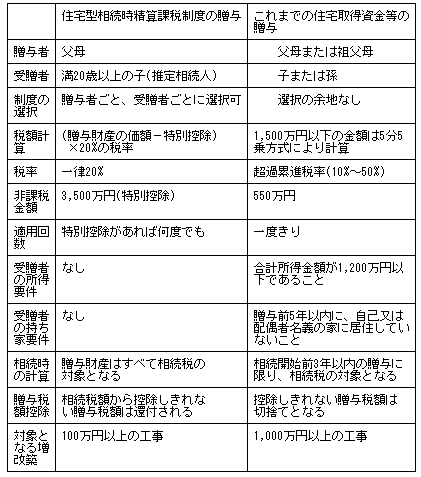
(3)住宅取得資金等との重複適用
これまでの住宅取得資金等の贈与特例の適用を平成15年1月1日以後に受けた人については、その贈与を受けた年以後5年間、その贈与にかかる贈与者からの贈与には、この住宅型相続時精算課税制度の適用を受けることができないとされています。
したがって、たとえば父親からこれまでの住宅取得資金等の贈与を受けた場合には、5年間はこの特例を受けることができず、6年目以降の贈与でなければこの特例の適用を受けることができません。
ただし、この取扱いは、平成15年1月1日以後に住宅取得資金等の贈与特例を受けた場合の取扱いですから、平成14年12月31日までに住宅取得資金等の贈与特例を受けている場合は、この限りではありません。
また、住宅型相続時精算課税制度の特例は、贈与者ごと、また受贈者ごとに選択適用ができますので、たとえば父親からの贈与には住宅型相続時精算課税制度の特例を受け、母親からはこれまでの住宅取得資金等の特例を受けるといったこともできます。
■金銭の贈与と住宅の贈与
金銭の贈与と住宅の贈与では、取り扱いが次のような違いますので、その特徴を考えてどちらの贈与をするか検討してください。
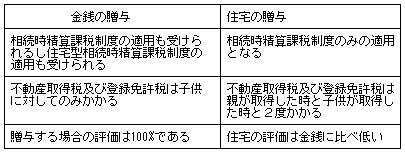
■一般の贈与との違い
住宅型相続時精算課税制度の贈与と一般の贈与とは次のような点で違いがあります。
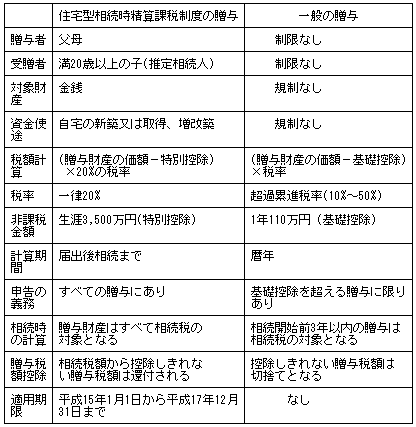
■特例の活用ポイント
この制度は、親から20歳以上の子供へ自宅の取得資金を贈与する場合に適用がある贈与の特例です。親には年齢制限がありませんから、子供が20歳になっていれば適用が受けられますが、資金使途は自宅の取得資金でなければなりません。しかし、この特例の適用を受けた親と子については、たとえ親が65歳になっていなくても、一般の相続時精算課税制度の贈与が受けられることとなっていますので、この取り扱いを活用すれば65歳未満であっても、自宅取得資金以外の財産を贈与することができます。
4.贈与税の配偶者控除
■概要
婚姻期間が20年(1年未満の端数は切捨てます)以上である配偶者から、次の居住用不動産等を贈与された場合には、基礎控除のほかに2,000万円(贈与財産の合計額が2,000万円に満たない場合はその合計額まで)を控除してくれる特例があります。これを贈与税の配偶者控除といいます。
(1)もっぱら居住の用に供する土地もしくは土地の上に存する権利又は家屋(居住用不動産といいます)で、贈与を受けた年の翌年3月15日までに受贈者の居住の用に供し、かつ、その後引き続き居住の用に供する見込みであるもの
(2)居住用不動産を取得するための金銭で、贈与を受けた年の翌年3月15日までに居住用不動産の取得に充てられ、かつ、受贈者の居住の用に供し、かつ、その後引き続き居住の用に供する見込みである場合におけるその金銭の額
この取扱いは、同一の配偶者からの贈与について一度しか適用を受けることができません。
■適用要件
この特例の適用を受けるには、次の手続きが必要になります。
(1)贈与税の申告書を提出すること
(2)贈与申告書に、この規定の適用を受ける旨並びにその控除額の明細を記載すること
(3)配偶者控除を受けようとする年の前年以前に今回贈与する配偶者からの贈与につき贈与税の配偶者控除の適用を受けていない旨を贈与税の申告書に記載すること
(4)贈与税の申告書に次の申告書を添付すること
①贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍謄本又は抄本及び戸籍の附表の写し
②その不動産の登記簿謄本又は抄本
③居住の用に供した後に作成された住民票
■相続開始前3年以内にされた贈与
相続又は遺贈により財産を取得した人が、その相続の開始前3年以内にその相続に係る被相続人から財産の贈与を受けている場合には、その贈与によって取得した財産の価額は、相続財産に含めて相続税を計算することとなっています(6を参照してください)が、この贈与税の配偶者控除の適用を受けた財産については、相続財産に含めなくてよいこととされています。また、この贈与があった年にその贈与をした者が死亡し、かつ、その財産の贈与を受けた者が相続財産を取得したときは、その居住用不動産の価額を贈与税の課税価格に算入することとして相続税の申告時に一定の手続きをした場合に限り、相続税の課税価格に算入されません。
■贈与活用のポイント
この贈与の特例を活用する場合のポイントは、次のような点です。
(1)2,000万円は取引価額ではなく相続税評価額によることから、金銭の贈与より自宅の建物、自宅の建物の贈与より建物の敷地の贈与がよい。
(2)夫婦ともに財産が多くて、どちらも相続税の最高税率が適用されるという場合は、この贈与を活用しても相続税の節税効果はない。
(3)将来自宅を売却する予定があるという場合にこの贈与をしておくと、譲渡時に居住用財産を譲渡した場合の3,000万円控除の特例が夫婦ともに受けられるというメリットがあるが、この3,000万円控除の特例は建物と土地をともに譲渡した場合に適用があるので、この適用を受けるには、土地と建物を贈与しておく必要がある。
5.相続開始前3年以内の贈与の取扱い
■概要
相続税法では、相続または遺贈(死因贈与を含む)により財産を取得した者が、
その相続開始前3年以内に、その相続にかかる被相続人から贈与により財産を取得しているときは、その贈与により取得した財産の価額をその者の相続税の課税価格に加算して相続税額を計算し、その計算した相続税額からその贈与時に課せられた贈与税額を控除した金額をもって、その者の相続税額とすることとされています。ただし、贈与税の配偶者控除の対象となる財産については、この取り扱いはありません。
なお、この場合の相続税の課税価格に加算する贈与財産の価額とは、相続開始時の価額ではなく、贈与時の価額となります。
■相続時精算課税制度の贈与の場合
相続時精算課税制度による贈与は、相続開始前3年以内の贈与財産だけでなく、それ以前の贈与財産すべてが相続財産に加算されます。
■贈与活用のポイント
この取り扱いの対象とならないためには、次のことに注意して贈与をしてください。
イ.贈与は、被相続人の健康状態などを考え、できるだけ早い時期に行う。
ロ.値下がりが予想されるものは贈与しない。
ハ.相続人以外(たとえば子の配偶者、孫など)の者に贈与をする。
6.負担付贈与、低額譲渡の取扱い
■負担付贈与の取り扱い
(1)概要
負担付贈与とは、財産に借入金などの債務をつけて贈与をすることをいいますが、この負担付贈与があった場合は、贈与された財産の価額から、負担額を差し引いた価額に相当する財産の贈与があったものとして取り扱われることとされていますが、この負担付贈与により、土地等(土地及び土地の上に存する権利)並びに建物等(建物及び付属設備又は構築物)を取得した場合には、その財産の価額は相続税評価額によらず、その取得時における通常の取引価額に相当する金額よって評価することとされています。ただし、土地等又は建物等を取得してから贈与するまでの期間が短期間であるなどから、贈与者が取得又は新築等した土地等又は建物等の取得価額がその課税時期における通常の取引価額に相当すると認められる場合には、その取得価額に相当する金額によって評価することが認められます。
※取得価額とは、その財産の取得に要した金額並びに改良費及び設備費の額の合計額をいい、家屋については、その合計金額から、償却費の額又は減価の額を控除した金額をいいます。
(例1)
・アパートの土地、建物 8,000万円(通常の取引価額)
5,500万円(相続税評価額)
・アパートに係る預かり保証金 500万円
アパートの土地、建物とアパートにかかる預かり保証金を負担付贈与した場合の贈与金額は次のようになります。
8,000万円-500万円=7,500万円
つまり、土地等又は建物等だけを単純に贈与する場合であれば、相続税評価額(この例であれば5,500万円)で贈与することができるけれど、負担をつけて贈与すると、通常の取引価額で贈与したこととなるわけです。
(2)預かり保証金の取り扱い
このように、賃貸アパートなどを保証金返還義務を負っている状態で贈与をする場合は、負担付贈与の取り扱いを受けるのですが、贈与時にその保証金返還債務に相当する現金を贈与する場合については、保証金返還債務を承継する意図がないと認められることから、この場合には負担付贈与の取り扱いをしないこととされています。賃貸アパートなどを贈与する場合は、この点に注意しておくといいでしょう。
(例2)
・アパートの土地、建物 8,000万円(通常の取引価額)
5,500万円(相続税評価額)
・アパートに係る預かり保証金 500万円
・現金贈与 500万円
例1に預かり保証金に相当する現金500万円を贈与した場合の贈与金額は次のようになります。
5,000万円+(500万円-500万円)=5,000万円
■低額譲渡の取り扱い
低額譲渡とは、いわゆる時価より著しく低い価額で譲渡することをいいますが、個人間で低額譲渡が行われた場合は、その譲渡があったときにおいて、その財産の譲受者がその譲受対価の額とその譲渡があった時におけるその財産の価額との差額に相当する金額を、その譲渡した者から贈与により取得したものとみなされることとされています。なお、この場合の財産の価額は、負担付贈与の取り扱いと同様に通常の取引価額よって評価することとされています。著しく低い価額かどうかは、時価などを参考に社会通念にしたがって判定します。なお、この取り扱いは、たとえば、現金で売買する代わりに譲渡した者の借入金を譲受者が肩代わりする場合などにも適用があります。
(例)
・アパートの土地、建物 8,000万円(通常の取引価額)
5,500万円(相続税評価額)
3,000万円(取得価額)
・譲渡対価 4,000万円
通常の取引価額が8,000万円のアパートの土地、建物を4,000万円で譲渡した場合は、譲受者に次の金額が贈与されたものとみなされて贈与税が課税されます。
8,000万円-4,000万円=4,000万円
一方、譲渡した者には、4,000万円の譲渡所得の収入金額があったものとして所得税が課せられます。
低額譲渡は、このように譲渡した者に譲渡税が課されるだけでなく、譲受者にも贈与税が課せられますので注意してください。
7.贈与と譲渡の違い
土地等、建物等を一般の贈与又は譲渡した場合の違いは、次のようになっています。